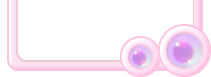むかしむかし、つきのめがみさまはいいました。
あなたに、しれんをあたえましょう。
そのしれんを、ともにうけるなかまをさがしなさい。
あなたが、そのしれんをこえることができれば。
あなたは、つくられたものではなくなるでしょう。
つくられたものではなくなるでしょう……。
なるでしょう……。
…………。
*
「……んっ……夢…………なんだ、夢かぁ……」
朝焼けが、目覚めたばかりの瞳に優しく差し込む。
ミルフィは半身を起こし、ぼーっと視線を空に浮かばせた。
それは、久しぶりに見た夢……。
毎晩のように、寝る前にせがんで読んでもらった絵本の話……。
ミルフィの一番お気に入りの絵本だったそれは今、書庫の一番奥に押し込み、ここ数ヶ月、背表紙すら見ていなかった。
毎日のように見ていたものだから、ここに来て思い出してしまったのだろうか。
そんな風に思いながら、ミルフィの胸の奥に、懐かしさと共に、寂しさが滲んだ。
「お兄ちゃんが全然連絡してこないからこんな夢を見るんだよ……」
ミルフィは、毛布の端をぎゅっと強く掴んで、胸の中にぽっかりと空いた穴を埋めるように、そう呟いた。
ウィルが地上に修行へ出かけて、1年……。
その間に、一度もウィルからの連絡はなかった。
家を空けがちなクロウフォードとの2人暮らしは実質1人で過ごす事の方が多い。
ただ待つだけの日々。
連絡すら寄越さないウィルの無事をただ祈りながら、毎日ゆっくりと過ぎる時間を待ちながら過ごす。
それがミルフィの今の全てだった。
大好きな兄の無事を毎日のように両親の墓に願う。
いつかきっと、ちょっと不機嫌そうなあの顔に抱きつき、キスをする時が来ると信じながら。
「でも……寂しいよ、お兄ちゃん……」
目覚め、隣のベッドにいるべき人影がない事を確認して訪れる喪失感。
眠れない夜にベッドに忍び込みしがみついた温もり。
優しく頭を撫でてくれる大きな手。優しい息づかい。
それは今、望んでも得られないものだった。
ミルフィはウィルのベッドがあった、今はなにもない場所を見た。
ウィルがいなくなって少し経ったある日、ミルフィは同じ部屋で共に暮らしていたウィルのベッドを退かしてみた。
それは、空のベッドを見ると悲しくなるから。
しかし、ベッドを片づけても、机を片づけても、クローゼットの中身を片づけても、悲しみは消えなかった。
がらんとした部屋を見つめ、ああ今自分は1人なんだという実感が湧き、1人ベッドで泣いた。
そして1年……。
寂しくても朝は来るんだと、納得できるようになったのはつい最近のことだった。
「……ご飯、食べなきゃ……」
ミルフィはそっとベッドから這い出、着替えを済ませて1階のリビングへ向かう。
*
リビングには誰もいなかった。
かわりに食事の用意と、街に用事があって出かけているという、クロウフォードの書き置きがある。
仕方なく、用意してあったお料理を食べながら、小さくため息をつくミルフィ。
「とりあえず、お洗濯かな。そのあとお掃除して……。やること、なくなっちゃうんだよね……」
ミルフィは黙々と食事をし、食器を片づけ、台所へ運ぶ。
そしていつも以上に時間をかけて食器を洗ってから、洗濯をするために、屋敷の裏の井戸へ足を向けた。
「今日もいいお天気ーっ。これならお洗濯ものもすぐ乾くよね、お兄ちゃ……あ……」
少し嬉しくなり、はしゃいで背後に声をかけ、振り返る……しかし、振り返ったそこにはもちろん誰もいない。
1年経った今でも、ミルフィは無意識に兄の影を追っている。
ウィルはいない。それは分かってはいるのに、なぜかその影を求める。
1年経った今でも、忘れることなく。
いつかは帰ってくる……。それが分かっていても、それでも……。
「もしかしたら、事故に遭ったのかな。それともわたしのコト、忘れちゃったのかな……。連絡くらいくれてもいいじゃない……。お兄ちゃんのバカ……」
毎日のように繰り返してきた問答。
その答えをくれる人は一度も連絡すらくれずに、地上にいる。
空中庭園に手紙が届くことは希だって事は、頭の中では分かっている。
でも、ミルフィやっぱり寂しいんだよと、洗い桶の上に、涙が生み出す水の波紋を見つめながら呟いた。
*
洗濯が終わったのち、昼食代わりに少し残しておいたパンを包み、ミルフィは出かける準備を始める。
最近の日課である、両親の墓参りに行くためだ。
両親の記憶は、実は殆ど残っていない。
両親は星になり、ずっと自分たちを見守ってくれている……。
ずいぶん昔にウィルが言った言葉通りの存在と、ミルフィは認識している。
だからミルフィは毎日のように両親の墓へ向かい、ウィルの無事を祈っていた。
屋敷から出て、通い慣れたなだらかな坂になっている細道を、丘に向かって歩く。
両親の墓までは少し歩かなくてはいけない。
屋敷の側の丘の上に、それがあるからだ。
ミルフィは散歩をするように、景色を楽しみながら、ゆっくり坂道を上がっていく。
空中庭園は常春の楽園だと、たまに来る冒険者は言う。
ミルフィの目に映るのは、数100年も代わり映えのしない景色らしい。
それは大昔、空中庭園を作った者により、全て定められたからだとクロウフォードが言ったのを覚えている。
が、魔法に興味のないミルフィはただ、いつも春にできる魔法がかかっているのだと認識していた。
それはあながち間違っていない。
そしてそれを学ぶことになるのは、これよりもう1年経ったのちであることを、この時のミルフィは知らなかった。
丘の中腹あたりへさしかかった頃、茂みの奥がかすかに揺れた。
「お兄ちゃん!? ……のワケないか……。だれだろ、今日はウサちゃんかな? ウサちゃんならいいな、おいで~♪」
空中庭園には小動物がたくさん生息している。
散歩の毎に、ミルフィは様々なかわいらしい小動物と出会い、顔をほころばせていた。
だからその時も、その中のなにかが近づいてきた物だと思い、包んで持ってきたパンを分けて与えようと、バスケットから取り出した。
それは、ウィルが修行を終え、この地に舞い戻る、少し前の話。
運命は時に残酷に、物語の始まりを告げる。
しかし、それを知るものは……今はいなかった……。