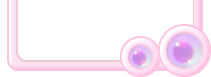「こっ、婚約者ぁぁぁ~!?」
突然言いだしたその言葉に、リュミは思わず手にした食器を取り落とす。
それだけの驚きを、そしてなにより思いもかけなかった言葉を、リュミは父から聞いたのだ。
「ち、ちょっと待ってよお父様っ、わたしまだ、結婚なんてしたくないわよっ!?」
これはしたない、と言う母親の制止も聞かずに立ち上がり、上座に座る父親に肩を怒らせ、ツカツカと近寄るリュミ。
そんなリュミを見て、あからさまに顔を引きつかせ、アワワと逃げ出そうとする父親……
まったく威厳のないこんな父親でも、割と大きな都市の統括者というのだから、世の中不思議なものである。
「というか、なんでいきなりそんな話になったワケ? 昨日までそんな素振りすらなかったじゃない……って、もしかして……」
リュミエールはそう言いながら、たった1つだけある心当たりに思い付き、全身で嫌悪感をあらわにする。
「まさか、またあそこのアホ親子が無理難題でもふっかけてきたワケ?」
ジト目で自分の父親を見るリュミ。
その父親の様子から大体を察し、はぁと大きくため息をついた。
「まったく、お父様はこのフェリオンの最高責任者でしょ? なんであのアホ親子にがつんと言わないのよっ!?」
あまりお父様をいじめないように、と言う母親の声を聞き流し、リュミエールはばんと強くテーブルを叩く。
「何度も言ってるでしょ! わたしはっ! あの親子がっ! 世界で一番大っ嫌いなのっ!!」
その鬼神のごとき勢いに思わず、まだ決定事項じゃないとわめきつつ、椅子からひっくり返る父親。
情けないことこの上ない。
何度も言うが、コレでも一都市を預かる最高責任者である。
気疲れからか、少々頭髪が後退したことを除けばそれなりに恰幅もよく、いい男の部類に入るであろう。
実際彼の手腕は確かで、魔法というものを認めようとしない地上の都市群の中で、魔導国家というものを確かに確立させ続けているのは称賛に値する。
しかしその実体が、娘と妻にまったく頭の上がらない恐妻家だというのを知る者は、実は殆どいなかったりする。
「確かにお父様の辛い立場は分かるけど。それでもそれで、娘の将来を決めて良いと思うの? というか、決めさせるワケないけど」
リュミはそう言い、ぎりっと奥歯を噛む。
魔法……。
それはこの世界における神秘の力のことである。
この世界の魔法は精霊の力を借り、一定の方向性を与えることで様々な力を発揮する。
それが魔法であり、殆どの人間がおいそれと使うことができないものである。
そのため魔導師は驕りやすく、また人々はそんな魔導師を恐れる。
それが地上における、魔法と人々の関係だった。
リュミエールはそんな世界の中でも珍しく、魔法を受け継ぎ世に伝えるフォンドベルテ家の長女として生まれた。
幼少の頃からたたき込まれてきた魔法というもの。そして自身の才能を、リュミエールは信じている。
そのプライドを持って、今まで魔法を覚え、切磋琢磨してきたのだ。
しかし、リュミエールが年を重ね美しく成長していく毎に、リュミエールにも政治の世界の暗部が重くのし掛かってくる。
それは、今までは両親が手前で押さえ込み、リュミエールが直接知ることはなかったものだ。
しかし、社交界にデビューし、世間に出るようになった今では、当然防ぎきることはできなくなる。
それでもリュエール自身の性格と、魔法というものの恐れから、俗に言うナンパ野郎は恐れおののき近づくことは少ない。
しかし、そんな中でも一部……というか、1人、しつこいヤツがいた。
バートラム地方でもかなりの豪商の一人息子で、事ある毎にリュミエールに絡んでくる男。
成金趣味でなおかつエロでタル体型、歯が全て金歯といういかにもな姿を思い出し、身震いするリュミエール。
おそらく今回の件はソイツが、同じくらい性格に難のある父親に頼み込んで起こった出来事なのだろう。
「それと、なんで今夜のパーティにアイツらが来るのよ? 招待しないでって言ったでしょ? 今夜はわたしの誕生パーティなのよ、あんなのがきたら、一気につまらなくなっちゃうじゃない。というか穢れるわ、わたしの思い出が、思いっきりっ」
やたらと憤るリュミに、父親が小さく、怯えたように言う。
「え……前回のパーティで、わたしがワインをぶっかけたコトを水に流すために仕方なく……って、わ、わたしのせいって言いたいワケ!?」
その言葉にうなずく父親の襟首をむんずと掴み、無理矢理立ち上がらせるリュミエール。
「た、たしかにわたしのせいかもしれないけど……今回ばかりはイヤだって念を押したでしょ!? それともナニ? お父様はあんなのが息子になるのを望んでるの!?」
慌てて首を横に振る父親を見て、その手を放してから、大きくため息をつく。
「……別に、お父様を責めてるワケじゃないけど……イヤ、責めてたけど……でも、今日くらいは……あんなの見たくないわよ……」
そう言い残し、リュミエールは小さくうつむいた。
そんなリュミエールの肩を、真っ白なローブに身を包んだ女性が優しく包む。
フェリオンの白き聖女……炎の魔女の2つ名を持つ、リュミエールの母親だった。
「なんだ、こんな所にいたのかい?」
ベランダで1人ぼーっと空を見ていたリュミエールに、鈴の音のような透き通った声がかけられる。
「……いちゃ悪い?」
振り向くことなくただじっと空を見続けていたリュミエールの横に、その声の主が立った。
「悪くはないよ。僕もここから眺める星空は好きだから……」
それは、女の子に見間違いそうになるような、綺麗な顔立ちの青年だった。
身に付けている衣装がドレスなら、十分美少女の部類に並ぶことができるであろう。
リュミエールの幼馴染みはリュミエールの横で、やはり同じように空を見上げる。
リュミエールには、同年代の知り合いがあまり多くない。
それはリュミエールの家系が特殊なこともあるのだが、大部分はその勝ち気な性格に辟易し、近寄ろうとしないからだ。
そんな中でこの幼馴染みの家族達とは、騎士の家系から来る豪快さも相まって相性がよかった。
そんな中でなぜか1人だけ大人しく、線の細い人物。
それが今目の前にいる、貴族の次男である青年……リュミエールが心を許せる数少ない人物であった。
「……相変わらず綺麗な顔ねぇ」
「リュミちゃんには敵わないけどね」
「男の子に負けたら立ち直れないわよ、まったく……」
その横顔にしばし見とれたあと、ため息をつき、ぼそりと言うリュミエール。
「アンタも男の子なら、少しは体を鍛えなさいよ。そこらの女の子よりも細くて可憐って、なんなのよ……」
「これでも騎士の家系だからね、剣術とかをやらないといけないんだけど。僕は体が弱いから、そういうのはにい様やねえ様に任せてるんだよ。見た目は……ねえ様に言って」
「アンリねえ様、アンタをオモチャにするの好きだもんね……」
「うん。結構困ってる。アスレイにい様みたいな恰好をすると怒るから……」
「その割には嬉しそうじゃない?」
「そうかな? そんな気は全くないんだけど。それに、腕力ではアンリねえ様に叶わないし……」
「性格的にも叶わないじゃない、まったく……」
「あはは……それを言われると困るけどね」
青年困ったように頭を掻き、そして懐から、丁寧に包装されている小さな包みを取り出し、リュミに差し出した。
「お誕生日おめでとう。こんなモノしか用意できなかったけど、もらってくれると嬉しいな」
「あ、ありがと……」
その満面の笑みに少し照れながら、リュミはそっと包みを受け取る。
「わ……紅焔珊瑚のネックレス……綺麗……」
リュミは包みの中からこぼれ落ちた赤い輝きを掲げ、月の光に当てた。
それは月明かりを受け、神秘的に輝く。
まるで、炎のように。
「リュミちゃんには赤が似合うと思うんだ。なんと言っても、炎の魔女の後継者だし、いつも炎の魔法ばかりだしね」
「ちょっと……その言い方だと、わたしが所かまわず魔法をぶっ放してるみたいじゃないの」
「あれ? 違ったっけ?」
「……なんかココで魔法の練習をしたくなってきたわ」
「ご、ゴメン、降参。僕が悪かったよ」
「まったく、人を破壊魔みたいに言わないでよね。でも……ありがと。ずっと大切にするわ」
リュミは青年の額を軽く指でつつき、家族くらいしか知らない笑顔を浮かべてこう言った。
「う、うん……」
少し照れながら返事し空を見る青年。
そんな横顔を見ながら、リュミは小さくため息をついた。
「はぁ……ホント、女の子にしか見えないわねぇ……アンリねえ様が女の子らしくなったら、こんな感じなのかしら」
「それって、嬉しくないんだけど……」
青年は苦笑しながら、そっとリュミを見てもう一度微笑む。
それは月明かりの魔力を抜きにしても、女の子であるリュミですら、ドキリとする妖艶さを持っていた。
「僕はアンリねえ様の理想なんだって。性格も、見た目も、ねえ様が望んでも得られない、宝物なんだって、いつも言ってる」
「アンタってアンリねえ様にかかると、まるっきりお人形さん扱いだもんね。いつだっけ、家の用事でアンタのお屋敷に行ったら、ものすごい美少女がいてビックリしたことがあったっけ」
「あ、アレは、ねえ様が無理矢理ドレスを……」
「その割にはお化粧とかしてたじゃない?」
「アレだって、僕が寝てる間に勝手に……」
「それだって、ちょっとは気付いてもいいんじゃないの? 『リュミちゃんいらっしゃい』って出てきても、ぜんぜん気付いてないんだも」
「僕の寝起きが悪いことくらい知ってるでしょ……」
「笑っちゃったのが、おじ様達もアンタを見て『どちら様でしょうか?』って真面目に言ってたことよね」
「笑えないよ……あれからしばらく、家族の視線が痛かったんだから……ねえ様はねえ様で何度も着せ替えしようとするし……」
「それだけ、愛されてるってコトでしょ。わたしには兄姉はいないけど……あの2人なら欲しいくらいだわ」
「いつでもあげるよ」
「そうそう、そーいうわけにはいかないでしょ。わたしがお嫁に行くとかならともかく」
「あ、う、うん、そうだね、そうかも……」
なぜか真っ赤になり、青年がわたわたと手を振る青年。
そんな青年を見てリュミは笑った。
心の底から笑った。
昼間のもやもやとした気持ちが綺麗サッパリ吹き飛んだことを心の中で感謝しながら。
「リュミちゃん、笑いすぎだよ……」
リュミの笑いが止まらなくなって久しく、さすがに不満そうに青年が文句を言う。
しかしそれでも、くすくす笑いが止まらずに、目に涙を浮かべながらリュミが謝る。
「ゴメン。でもしょうがないじゃない。ホントに面白いんだから」
「むぅ……」
憮然とした顔のまま、青年がふてくされる。
その表情が女の子にしか見えずに、リュミは耐えきれず吹き出してしまう。
「アンタのおかげで助かったわ。色々あってつまらなかったんだけど、今日の誕生日のコト、いい思い出になりそうよ」
「それはそれは、光栄なことです。お姫様」
「よろしいっ」
恭しく、臣下の礼を取る青年。
それをニコニコ笑顔を浮かべながらそれを受けたリュミは、そのまま青年の腕を引き寄せ、会場へ誘う。
「それじゃ、お姫様からの命令を伝えます。臣下はこれから、姫様のダンスの相手をするコト。拒否権は当然ありませんっ」
「えぇ? 僕がそういうの苦手なの知ってるでしょ?」
「口答えは許しませんっ。ああそれと、いつものアレがたぶんスゴイ勢いで絡んでくるけど、体を張って守るコト、いいっ?」
「えええ? そ、それもまた僕の役目なの??」
「当たり前でしょ、アナタはそんなでも一応騎士なんだからっ」
「家は騎士だけど、僕は見習いですらないよ」
「ナニ言ってるのよ、アナタはわたしの騎士、でしょ?」
「……僕はたまに、リュミちゃんのそのポジティブな思考が羨ましく思うよ」
「どーいう意味よ、それ」
「深い意味はないけど。まぁ、あの人の相手はちょっと嬉しくないけど……僕まで変な目で見るし……」
「それも騎士の務めでしょ。それにアイツ、とうとう婚約とか言いだしたし、ここらでがつんとコッチの気持ちを示さないとね」
「え……こ、婚約……?」
「どうも今回は、お父様経由の絡め手で来たみたい。ウチのお父様の気の弱さにつけ込んで、許せないわ、あのタの字無し親子っ!」
「た、タの字無しって……」
「要するに、タヌキ親子ってコトっ!」
「ああ、なるほど」
「わたしはね、結婚なんかしたくないの! そりゃ、いつかは結婚したいなーとか思ってるけど……それでも、あんなヤツとはイヤっ!!」
「そっか……イヤなんだ……」
「当たり前でしょっ!? あんなのと結婚するなら、アナタと結婚するわよっ!」
「えっ?」
「ちょ……て、照れないでよ、モノの例えなんだからっ!」
「あ、う、うん……」
「アナタも騎士なんでしょ? 家柄とかじゃなくて、今はわたしの騎士なんでしょ? ならシャンとするっ! あたしだけの騎士なのよ? もっと誇りなさいっ!」
「そうだね……頑張るよ。僕はリュミちゃんの騎士だもんね」
「そうよっ! だからあの気色の悪い高笑いが聞こえるまでは、ダンスにつき合いなさい、いいわね?」
「分かったよ、頑張ってみる‥‥僕は騎士になれるんだもんね……今だけは、騎士に……」
青年はそう言って、リュミの手を強く握り返した。
少女はやがて、いくつもの戦いを経て、母である炎の魔女の名を継承する事になる。
しかし、今はまだ……その才能を眠らせたまま軽やかに踊る。
煌びやかな光の中で、まるでフェアリーリングの中央で舞う、精霊女王と見間違えるかのように、可憐で、美しく……。