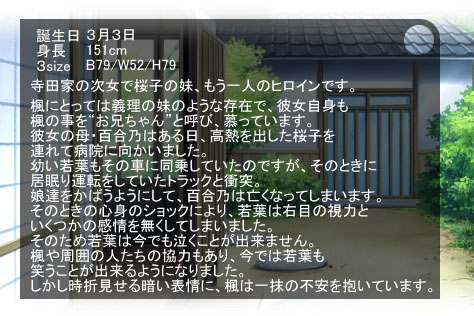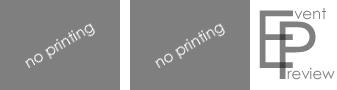| 学園からの帰り道。 少し遠回りして、駅前の商店街を通る。 目的もなく歩いてお店を眺めたり、おしゃべりをしたり。 「若葉ちゃん、今週は犬型のパンみたいですよ?」 「ほんとだ、可愛いよね、犬。なんの種類かな?」 「でもそう考えると、なんか食べるの、気が引けちゃいますね」 「あ、そっか」 これって寄り道、って言うのかな? 学園の帰りに、駅前に来たのは初めて。 ううん。友達と一緒に来たのは、かな。 今までは、そういう友達がいなかったから。 自分から……遠ざかっていたから。 学園ではなんとなく、みんなの“輪”に入ることが出来なかった。 テレビの話題や、本のこと、恋愛のこと。 そういう話に疎かったせいもあるけれど。 でも、それだけじゃなくて……。 なんとなく、その輪に入ってはいけないような気がした。 みんな仲良くしてくれているのに、でも、一緒にいちゃいけない。 自分の気持ちとは関係なく、どこかでそんなことを思っていた。 でも…… 「若葉ちゃん、ぬいぐるみキャッチャーですよ、ほら!」 「これ、難しいよね? 一回も取ったことないんだ」 「よーし。若葉ちゃんの為に、どれか一つ取っちゃいましょう!」 「え、と、とれるの? これ凄く難しいよ?」 「ふっふっふ、任せてください。あたし、こーゆーの得意なんですから!」 葎華ちゃんに対しては、そんな気持ちを持たなかった。 ボランティアの時、初めて見たときから。 なんか、凄く……似てるなぁ、って。 外見とか性格とか、まるっきり正反対だったのに。 ただ漠然と、似てるって……親近感っていうのかな、これ。 でもそのおかげで、葎華ちゃんと私は、仲が良くなったのかもしれない。 はっきりとした理由は、今でもわからないけれど。 : : : 葎華ちゃんと並んで、公園を歩く。 私の腕の中には、犬のぬいぐるみ。 さっき葎華ちゃんがとってくれた物。 「ホントにいいの? 貰っちゃって」 「もちろん! 100円しか使ってませんし……それに愛しの若葉ちゃんのためなら、あたし自身すらあげちゃいます!」 「あ、あはは……それは遠慮しとくかな……」 「もう、遠慮しなくても全然いいのに……」 「葎華ちゃん……どこまで本気だかわからないよ」 「あたしはどこまでも本気ですよ?」 明るい葎華ちゃんを見ていると、不思議と元気が沸いてくる。 まるで私、葎華ちゃんから元気を貰ってるみたい。 昔、楓お兄ちゃんから色々な気持ちを貰った時みたいに。 葎華ちゃんからも、なにかを貰っているような、そんな気がする。 こういうのが、友達、っていうのかな? うーん、ちょっと違うかな……。 「あ……」 そんなことを考えていた時だった。 不意に、葎華ちゃんの足が止まる。 少し先の、下を見ている。 その視線の先──地面には、子猫。 遠目からでもわかるくらいに、不自然に横たわっている。 「これ持ってて」 「あ、若葉ちゃん!?」 ぬいぐるみを渡して駆け寄ってみるけれど……もう冷たい。 お腹が動いてないし、口元に血が付いている。 なにより……体が冷たくて、硬くなってしまっていた。 「死んでる……」 「死んじゃってる、んですか……可哀想……」 「かわい、そう……?」 「……え?」 「猫、埋めてあげないとね……」 「え? あ……そ、そうですよね……埋めてあげなきゃ……」 可哀想……。 かわいそう……。 死ぬことは、かわいそうなこと、だよね……。 かわいそうなことは、悲しいこと。 じゃあ、死ぬことが、悲しいと思えない私は……。 やっぱり、心が壊れてるのかな……? 私はお母さんの顔を覚えていない。 お母さんは、私が小さい頃に交通事故に遭って、死んでしまった。 そのとき私は、お母さんと同じ自動車に乗っていたというけれど……。 それすら覚えていない。 だって、お母さんの記憶は……最後の涙と一緒に、流れていってしまったから。 心の中の“大事な何か”と一緒に、消えてしまったから。 だから私は、お母さんの顔を覚えていない。 だから私は、泣くことが出来ない。 そんな人って、たぶん私だけだから。 だからみんなと一緒にいちゃいけないって、思うのかもしれない。 葎華ちゃんとも、一緒にいちゃいけないのかもしれない。 だって私は、変な人だから……。 死ぬことが、悲しいって思えないんだから……。 「若葉ちゃん……若葉ちゃん……?」 「え、あ……ごめんね、ぼーっとして……ん、これでよし……」 「若葉ちゃんは、優しいですね」 「そう、なのかな……」 「……あたしは、そんな若葉ちゃんのこと、大好きですから」 「えっ……ど、どうしたの、いきなり?」 「ふふふ……何でもないです。それではまた明日、学園で!」 「あっ……う、うん、またね!」 そんな考えが、顔に出てたのかな……。 葎華ちゃんに突然、好きだって言われちゃった……。 私、元気づけられたのかな……。 でも……私の“変な部分”を知ったら、葎華ちゃんはどう思うだろう。 その考えは、夜……お布団に入っても消えることは無かった。 |