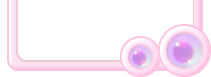少女はいつものように、お気に入りの場所で瞑想を行っていた。
ただ静かに目をつぶり、自然と一体化していく様は、殆ど老獪な魔術師のレベルである。
それは、修行を始めてたった数年である少女が、
どれほど血の滲むような修行を行っていたのか……それを物語っている。
少女が師と住む館は、この地方において魔女の森と呼ばれる樹海の奥にある、
一際大きな「世界樹」と呼ばれるトリネコの木の麓に建てられている。
幾重にも貼られた迷いの結界と、魔獣や精霊の多さ、森本来の深さ、
そしてそこに住む魔女の噂のために、踏む込むものが皆無の森……。
それが今の、少女の故郷だった。
バートラムの故郷より離れ幾年。あの日、全てが終わり、また始まった日より、
この故郷の森よりも高く、鬱蒼と茂ったこの森が、今の少女の世界となっていた。
どちらかといえば、少女がこの森にとけ込んでいると言った方が正しいのかもしれない。
音が、光が、木々が全て、少女と同化する。
今、彼女の肩に止まる小鳥たちも、おそらく彼女が人間ではなく、ただ体を休める木々と感じているのだろう。
それほど、深く、深く……瞑想を続けていた。
その日、アルエットは魔法の基礎訓練を終え、町人の依頼により森を出払っていた師を待ち続けていた。
屋敷は少女1人で入るには広く、様々な怪しい道具や標本、書物などが所狭しと並べられている室内は、
まだ幼い少女を怯えさせるのに十分な雰囲気を持っていた。
しかし、少女はそんな室内で、ただじっと師の帰りを待ち続けていた。
それしかすることがなかったから。
そう。少女にできる事は修行と、ほんの少しの家事。そして師を待つ事だけだった。
少女が知るのは森の中の世界と、屋敷と、魔法の修行の事だけ。
その修行すら、本当に成果を上げているのか分からないほどのものだった。
そう、少女はまだ一度たりとも魔法を扱った事がなく、そして精霊の姿すら、見た事がなかったのだ。
師の元で修行して少女が知った事。
それは、魔法というものがかなり融通の利くモノであるという事だ。
通常、魔法は呪文により精霊に働きかけ、その精霊に術者のマナを分け与える事で、呪文で定められた効果を発揮する。
しかし、その呪文というものは師曰く「かなりおおざっぱ」なもので、術者が手を加える事で効果を変更する事ができる。
例えば今、少女が使用している風の魔法は本来、巨大なオーガすら空へはじき飛ばす威力を持つものである。
しかし術者の意思により、呪文に変更をくわえる事で「竜巻」から「かまいたち」程度の威力に抑える事ができるのだ。
だから魔術師は魔法を研鑽錬磨し、独自の効果を発揮する魔法を生み出すのを、至上の喜びとする。
しかし、少女の師は、少女に魔法の基礎を教えたあとは、戦うための魔法ばかり彼女に教え込んだ。
いかに効率よく魔力を絞り出せるか、いかに効率よく敵を殲滅するか、いかに魔法の威力を最大限発揮できるか……。
そんな知識や基礎修行ばかり、少女はたたき込まれてきた。
文字通り、血の滲むような努力で。
常々、彼女の師は、少女の事を「才能のない者」と呼んでいた。
それは単に自身の努力が足りないのだと少女は思っていたが、実はそうではないらしい。
少女が魔女により拾われるまで、少女は魔法とは縁のない生活をしていた。
魔法という概念すら、知らなかった。
魔法がほんの一握りの者にしか使用できない特権である事も、
魔法を扱う才能はそのまま魔女の血に繋がる事もまた、知らなかった。
だから少女が、今でも魔法が使えなのは、当たり前だと思っていた。
そもそも魔法を扱うためのマナは、この世に存在する全てに宿っている。
しかし、そのマナを自らの意思で扱えるかというとそうではなく、
各々の才能や特別な条件下の元でのみ、マナというモノを具現化できる。
それを常時可能にするためのモノが「呪文」であり「呪文」により発動する魔法は「精霊」の力によるモノである。
つまり、いくらマナや呪文を持ち得ようと、精霊が力を貸さない限り、
それは「魔法」たりえないのが、この世界の魔法の構図である。
では、精霊はどうすれば自身に力を貸してくれるのか。
修行を始めたばかりの少女は、そのことがどうしても理解できなかった。
そんな少女に、魔女である師はこう言った。
「精霊は魔女の血を持つ者に対してのみその力を貸す。遥か昔、古の魔女と精霊達との間に取り交わした契約の元に」
では、血を持たぬ者はどうなるのでしょうか……。
当然と言えるその質問に、魔女は少女の頭をぽんぽんと叩き、
表情の殆ど見えないフードからわずかに見える口の端をわずかに楽しそうに歪めて、こう言った。
「方法はいくつかある。一番簡単なものは特定の精霊を強制的に捉え、
無理矢理使役する方法……これはあまり勧めはしない」
なぜ? という問いに、師はあまり語りたくないように一言だけ、
遥か昔、それをしようとして滅亡しかけた種族がいるのだよ、と答えた。
「そして、魔女の種子を、受け継ぐ事……とはいえ、コレができる才を持つ者は、片手に足りるのだがな」
だから少女は、そのとき師が言った、もう一つの道を選んだ。
それはつまり、精霊がその者に敬意を表するようになるまで、己の力を鍛え上げるという道。
幼い彼女が選んだ、たった1つにしてもっとも過酷な道のり……。
何度泣いたか分からない。何度死にかけたか分からない。
それでも少女は黙々と修行に明け暮れた。
やがて、夢すら殆ど見なくなり、涙すら忘れ、苦しみすら日常になった。
だから少女が、やる事が無くなり瞑想の修行を始めたとしても、誰もとがめられないだろう。
それが、少女の全てなのだから。
瞑想を始めてどれくらい経っただろうか。
時間の経過すら曖昧になった頃、少女の前に、不思議な気配が立ち上った。
それは始め、蜃気楼のような存在だった。
それがゆっくり幻影から実体に身体を構築した時、目の前にいたのは、小さな……。
おとぎ話に出てくる竜のような姿をした精霊だった。
「ソレ」は始め、じっと少女を見つめていた。
少女もまた瞑想のポーズのまま、黙って精霊を見つめていた。
やがて精霊は、少女に問いかけた。
それは頭の中に直接響くような不思議な声で……少女はとても綺麗な声だと思った。
『チイサキモノヨ オマエハナゼ コウマデシテ マホウヲ モトメル?』
精霊はそう言って、少女を見た。
少女はなにも答えずに、精霊をじっと見つめ続ける。
そんな少女の右隣に、熱気と共に小さな炎が舞い上がった。
それが人の形になり、緑の竜とは違った荒々しい声で問いかける。
『汝が求めるは、破壊か?』
その問いにも少女は答えず、ゆらゆらと揺らめく炎を見る。
そんな少女の左隣に、今度は大きな水滴が現れ、人型となる。
それは女性らしい流線型の身体を持って、見た目と同じように優しい声で問いかける。
『貴女が求めるのは、癒しですか?』
女性らしいその声にも少女は答えない。
そんな少女を見て、女性は少し悲しそうな顔をしてほんの少し身を引いた。
それと共に、少女の背から、巨大ななにかが蠢く音が響いた。
『少女よ、なぜ答えぬ? 人が魔法を求める理由を星の数ほど聞いてきた。
それらは皆、なにかしら目的があったものだぞ』
それは砂や岩がこすれるような不思議な音と共に、少女に問いかける。
その問いに……少女は一度目をつぶり、小さく、答えた。
「……することがないから」
4つの気配がざわざわと、とまどうようにざわめく。
『なるほど……ルーンの危惧するとおりの結果であるな』
砂のような、岩のような声がそう言う。
『感情と才能は反比例するものではない。むしろ、感情的にならない術者の方が優秀と言えよう』
炎のような声が、それに反論する。
『火の者の考えそうな答えですわね。わたくしはむしろ、慈愛を知らぬ心に育たぬ事を危惧しますわ』
水の女性が少し悲しそうに言う。
『ソレハ ワレラガ オシエル モノニ アタワズ ワレラガ ナスベキハ ケイヤク ノミ』
緑の竜が、鈴の音のような声でそう言う。
『ショウジョヨ……イダイナル、ルーンノナヲツグモノヨ……』
『我らは汝に問おう』
『貴女が欲する力は、世界を滅ぼす事も、救う事もできる力となりうるものです』
『我らは少女に問おう。少女が求める力を、少女はなぜ必要とするのかを』
4つの声が少女に交互に問いかける。
それを聞きながら、少女はなぜ、修行を始めたのか……それに思いを馳せた。
少女が覚えているのは、ただ動かなくなったたくさんの人々の、苦悶の表情のみ。
自分の名前も、家族の事も、住んでいた村の事も、なにもかも覚えていない。
ただ、全てが死に絶えた地獄から、自分を救ってくれた師へのため……。
魔法を覚えようと心に誓った事を思い出した。
「……戦うために」
少女は呟くようにこういってから、目を見開いて4つの声の主を見た。
そこには、炎が、水流が、大岩が、そして竜巻がいた。
それが精霊なのだと理解した時。少女はこう言った。
「私を必要としてくれた人のために。私は魔法を使いたいです。
戦う運命にあるというなら、私はそうします。
人を救うために力を振るうのなら、ためらわずにそうします。
全ては私に道を与えてくれた魔女のために……私は魔女たる力を使います」
毅然としたその言葉に、炎が、水が、風が、土が、それぞれ形を変えていく。
『汝の勇気に敬意を表し、ならば我は力を貸そう。
我は炎にして全てを焼き尽くす者なり。我の力欲する時、いつでも呼ぶがいい』
炎が少女の身体を中心に渦巻き、消えた。
『炎の者と同じというのが、いささか不本意ですが……わたくしも力を貸しましょう。
わたくしは水にて命を育む大いなる海なり』
水もまた、炎と同じように渦巻き、消えた。
『少女よ。我が大地の力もまた、少女に預けよう。汝が欲する時、いつでも呼びかけよ。
我は大地にして盤石なる者なり』
岩は流砂となり、渦巻いて消えた。
『ワレモマタ チカラヲ カソウ』
風がやはり、鈴のような声で、少女に言う。
『ワレハ カゼニテ スベテヲ キリサキ ウチクダク モノナリ』
風はそう言い残し、消えた。
しかし、少女には理解できた。
それらは今、アルエットの心の中に存在する力であると。
自身の体内でゆっくりと渦巻く力……それがマナなのだと、なぜか理解できた。
依頼をこなし屋敷に戻った師は、少女を見るなり、目を細める。
「……そうかい、とうとう認めさせたのか」
そう言った魔女の声は、嬉しそうな、それでいてどこか悲しそうな声だった。
魔女がフードを取り、しゃがんで少女の瞳をのぞき込んだ。
ブロンドの美しい髪が、窓から降り注ぐ光に反射し、とても美しく輝いて、少女の頬をくすぐる。
逆光でその顔はよく分からなかったが……とても美しく、
まるで女神様のような……母親のようなものだと、少女は思った。
「我が最初にして最後の弟子よ。我が名を受け継ぎし、魔女たる才能なき者よ……。
しかしお前は努力の才能にて、その壁を乗り越えた」
そう言って、魔女は少女を抱き寄せる。
その身体はとても優しく、若草のような匂いが少女に届く。
「明日から、実戦の修行を行う。覚悟はいいか、アルエット……?」
魔女はそう言い、最後に小さく、なにかを呟いた。
とても小さく、聞き取れない短いフレーズ。
ただ……とても心に染み入るような、優しい言葉……。
アルエットと呼ばれた少女が、その魔女の言葉を思い出すのは、これより数年後の事である。