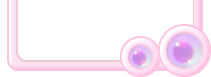空中庭園……。
それは俺の第二の故郷にして、唯一の帰るべき場所。
しかし今は帰るわけにはいかない。
修行のこともある。だが俺には断ち切らねばならないコトがあるから。
それは……。
「……ねぇ、ちょっと、ウィルっ」
草むらに寝転がり、空を見ながら故郷を思っていた俺は、少し不機嫌そうに呼ぶ声に、唐突に現実世界に引き戻された。
「ん……? ああ、スマン、なんだっけ?」
「なんだっけ、じゃないわよ、もうっ」
俺を雇ったパーティのリーダーを自称する女性……。
というより俺より年下の少女が、いつもの不機嫌そうな顔で俺をにらみつける。
やたらと露出度の高い服と、短いスカートを見る限り、これっぽっちも冒険者に見えないのが不思議だ。
……白い下着が丸見えなのは、教えた方がいいのだろうか。
「まったく、こんな所で昼寝してないで仕事しなさいよね、し・ご・とっ」
そんな事を考えていた俺に、少女がきつい言葉を投げかける。
「……………………」
……教えるのは中止だな、うん。
「偵察はスカウトの仕事だろ。俺は遺跡内での化け物退治に雇われたはずだが?」
少し不機嫌な口調で、俺は少女に言葉を返す。
「索敵ぐらい、魔法でできるでしょ」
「索敵と言われても、せいぜい、結界内に進入してきたモノの感知くらいしかできないぞ」
「それならそれをしなさいよ……って、え……? 結界……?」
「言われなくてもやってますよ、依頼主様」
おどけたように言う俺を見て、きょとんとする少女……。
名前は聞いたが覚えていない……が、急に真っ赤な顔をして喚いた。
「やっ、やってるならやってるって言いなさいよっ!?」
「やってないとも言ってないだろ?」
「そ、それはそうだけどぉ……じゃなくてっ! リーダーのあたしにちゃんと報告しなさいってコトっ!」
「なにもいないよ。せいぜい野ウサギが数回進入してきたくらいだ」
「く、くぅ~……っ」
「……気を張りすぎだ。今からこんな調子だと、遺跡に入ってからもたないぞ」
「よっ、余計なお世話よっ!」
吐き捨てるように怒鳴り、大股で宿営地へ戻る少女。
「……気にしてくれるのは嬉しいんだがな」
俺はそう呟き、大きく息を吐く。
久しぶりに人間扱いされた事が嬉しくもあり、また悲しくもある。
それは宿営地から俺を見つめる、少女以外の視線からして明らかであった。
地上における魔術師の扱いは、想像以上にひどい。
師匠とミルフィ以外、殆ど顔を合わせる事のなかった空中庭園の修行からは決して想像できない現実。
それでも買い物のために町に出ると、胡散臭そうな視線を浴びたものだが、ここまで露骨ではなかった。
空中庭園には幾多の冒険者が集い、冒険者のための街が存在する。
胡散臭そうに思われるのは師匠のせいだから仕方がないにしても、人々はそれなりに普通に、俺や魔導師を受け入れてくれていた。
しかし、それだけが世界の全てではない事を、俺は地上に降りてイヤと言うほど思い知った。
地上における魔法という存在は、未だ神秘なる力で、かつ恐怖の対象であった。
それは、強大な力を持つ魔術師のエリート然とした態度や、魔導師が魔力に溺れ闇に堕ちる者が多い事、そして闇に堕ちた者達は例外なく、人に対して悪意を持つ事など、原因は色々ある。
どちらにしろ地上では、殆どの者は魔法を胡散臭い力だと思っていると考えていい。
実際俺も、魔術師だという理由のみで殺されかけた事も、救世主扱いされた事もある。
幸いな事に、俺が使う魔法の触媒が指輪のために、目深なフードつきマントを被っていれば、ただの冒険者にしか見えない。
だから俺は、普段は冒険者として活動し、路銀が足りなくなった時などに、少しだけ魔法の力を使い、キャラバンの護衛や魔物退治などを行っていた。
今回の護衛の仕事も、路銀が足りなくなった所で立ち寄った街で、少女と偶然知り合ったのが縁だった。
その少女は、5、6人の荒くれ者に囲まれても、一歩も引かずに対峙していた。
ギャラリーはそれを、巻き添えにならないように遠巻きに眺めているだけ。
このご時世、どこに行ってもよく見かける図式だ。
普段は見て見ぬ振りをするか、スリープの魔法でもこっそりかけて立ち去っている所だ……。
しかし……その時の俺はなぜか、その少女の前に立ち、鼻息荒い男達と対峙していた。
*
「なんだぁ、お前は……?」
理由は今でも分からない。ただ……少女の髪がなんとなく、妹の髪型に似ていたから……そんな理由だったと思う。
ただ、男達は目の前に立つ華奢な俺を見て、明らかに面食らっていた。
見た目からして山賊然とした男が、俺を見て怪訝な顔をしてから、すぐに小馬鹿にしたような笑みを浮かべ、醜い顔を近づける。
「大人の話に割り込むんじゃねぇぜ、優男さんよぉ? それともなにかい? その細腕でオレっちとやり合おうってか?」
「……………………」
「女の前だからといって、かっこつけてると怪我するぜぇ? げへへへへへっ」
「……………………」
「なにだんまり決め込んでるんだ? もしかしてオレらが怖ぇのか、情けない男だなぁ、げへへへへっ」
「……アンタ」
「あん? なんだ、優男?」
「アンタ、いつから歯を磨いてないんだ?」
「な、なんだそりゃ?」
「息が臭いって言ってるんだよ」
「なっ、なんだとぉっ!?」
俺の挑発にすっかり息を荒くした男が、その丸太のような腕を振り上げる。
しかし、それ以上の事はできずに、明らかに狼狽した顔で、唾を飛び散らせながら喚いた。
「なっ、なんだぁ!? かっ、身体がうごかねぇ!?」
「まったく、耐性のないヤツはあっという間にかかるから面白い。それはパラライズという魔法だよ」
「ま、魔法だと……ちゅーことは、まさかお前は魔術師……」
「まさかとは失礼だな。正真正銘、魔術師だよ」
その言葉と、俺が指先に呼び出した光の精霊の輝きに、男とその仲間の顔色が、一気に変わる。
「ま、まじゅつしだぁ!? に、逃げろ、殺されて実験材料にされちまう!!」
「ま、待て、お、おいていかないでくれよぉ!?」
失禁し、鼻水と涙で顔を醜く歪ませる男を見ながら、俺は小さくため息をつく。
「まったく、やられ役ならやられ役らしく振る舞えよな……『キュア・コンディション』……」
「ひっ、ひぃぃぃぃっ!?」
解呪の魔法を受け、へなへなと座り込んだ男は、四つん這いのまま必死に逃げていく。
男が視界から消えるのを確認してから、俺は絡まれていた少女を見た。
長い亜麻色の髪を左右で縛った少女……。なるほど、遠目で見れば似てなくもない。
しかし少女は可愛いというより、美人系の顔で、幼い妹の顔しか覚えていない俺からしてみれば、やはり別人の顔だ。
そんな少女がぽかんと口を開けて、俺を見つめていた。
それが驚愕なのか、それとも畏怖なのか……いや、どちらでも別に関係ない。
俺はおどけるように肩をすくめ、この場を立ち去ろうときびすを返す。
……が、そんな俺のマントを、少女はがっしり掴み、引っ張った。
「すっ、すごい! あたし、魔法って始めて見たよ!」
「……は?」
想像していた反応と違うその少女を見て、思いっきり面食らう俺。
「アンタ、名前は?」
「へ?」
「だから名前。あ。名前を尋ねる時は、自分から名乗るべきだよね。あたしの名前は……で、アンタはっ?」
「お、俺……?」
「そうよ、名前くらい教えてくれてもいいわよね?」
「う……ウィル」v
「へぇ、結構男らしい名前なんだっ? ねね、ウィルってやっぱ、どかーんとなる魔法も使えるのっ? それって見せられる? あ、でも町中じゃまずいか、街から出たら見せて欲しいなっ」
「あ、ああ……いや……」
「あ、もしかして冒険者ギルドに行こうとしてた? 実はあたしもなんだけどね、途中であんな変なのに絡まれちゃって。ホント、ウィルのおかげで助かったっ。まぁ、アレくらいなら簡単にノシちゃう自信はあるんだけど、よくお父ちゃんに、お前はおてんばすぎるって言われてたから、最近あんまり剣の修行してないのよね。あ、でもでも、あたし結構剣の自信あるの。だから今回の仕事も、手が離せないお父ちゃんのかわりに行く事になったんだけど……。って、ちょっと、ちゃんと聞いてるっ?」
少女は自己紹介してから、一気にまくし立てるように言う。
「って。冒険者ギルドに行くって事は、仕事を探しに来たのよね? それならいい仕事があるんだけど……乗ってみない?」
その少女が有無を言わさぬように俺に詰め寄る。その勢いに負けて、俺はなぜかうなずいていた。
そして……。
今に至るわけである。
*
「はぁ……この押しの弱さ、なんとかしないとな……。上では師匠やミルフィにいいようにこき使われてたし……。大体、家事を弟子がやるのはいいとして、なんでミルフィの分まで俺がやってたんだろ……。なんかトラウマクラスな理由があったような気がするが……。なぜだろ、思い出せないな……」
半ば……というか成り行きでパーティを組み、共に遺跡にもぐってから1刻ほど過ぎただろうか。俺はため息と共に、薄暗い遺跡を見た。
元々神殿として機能していたこの遺跡はかなり広く……。そして、静かだった。
俺はパーティの殿(しんがり)に位置し、先行するスカウトの仕事ぶりをのんびりと眺めていた。
パーティに遺跡に関しての情報があるのか、スカウトが馴れた手つきで罠を外し、屈強な傭兵が周囲を警戒している。
俺に与えられた仕事は魔物の牽制……。前任のパーティが全滅した事から、いるらしいという予想だけなのだが……。
しかしそれも、今の今まで欠片すら気配がないうえに、魔物特有の黒い波動の感覚すら感じない。
つまり……ヒマだったりする。
パーティと俺との中間にいた少女が、ちょくちょく俺の様子を盗み見ていたのは気付いていたが、俺はあえて気付かない振りをしていた。
どうも彼女は、俺の使う魔法に興味があるらしい。
まぁ、気持ちは分からない事もない。
魔術師など、ここ1年各地を放浪した俺ですら、片手で足りるほどしか出会っていない。
まだ若く、色々な事を知りたがる年頃の彼女からして見れば、俺はさながら、おもちゃ箱のようなモノなのだろう。
だからといって、マジックのようにほいほい魔法を見せる気は毛頭ない。
もしも見せる時が来るのなら、それはたぶん、パーティの面々が対処できないような魔物が現れた時……。
特に剣戟の効かぬゴーストやレイス、狂った精霊などが現れれば……。
なんとなくそんな事を考えながらふと前を見ると、俺は少女に、あからさまにじーっと見つめられていた。
「………………」
「………………」
「……………………」
「……………………」
「…………なんだよ?」
俺は結局根負けし、少女に声をかける。
そんな俺に、少女はしれっと答える。
「見てただけ」
「……………………」
「魔法、使ってるの?」
「厳密には魔法ではない。風の精霊に異変を探らせてる……といっても分からないか」
「ん~……あたしにはそういうの見えないし。お父ちゃんは見えてたみたいなんだけど」
「見えていた……? 精霊が……?」
「うん。精霊は見えないだけで何処にでもいるって、いつも言ってたわ」
「精霊は、魔女の血を持つ者か、精霊に祝福された者にしか見えないのだが……」
「そうなの? お父ちゃんは魔女の血なんか無いって言ってたけど」
少女が少し小首を傾げ、頬に指を添えて考える。
「それならたぶん、フェアリー・アイだな」
「……なにそれ?」
「精霊に見初められた者だけが、その身に宿す『ギフト』の事だ」
「余計分からないんだけど……」
「お前のオヤジさん、左右の目、金銀だろ?」
「え、ええええええええっ!? な、なんでわかるの!?」
「それが『ギフト』だ。生まれ持った不思議な力と言えばいいのかな。金銀の瞳を持つ子供は、精霊に祝福された子供だと、昔師匠に聞いた事がある。それは『ギフト』と呼ばれ、人とは違った力を持つ。癒しの力、飛行の力、水を操る力……力はそれぞれだけどな」
俺は難しそうな顔をしている少女に、できる限りわかりやすいように説明する。
「その中でもフェアリーアイ……『妖精眼』は、生まれついて幻視の力を持つ。これがあると霊的なモノや、マナに関するモノを普通に視る事ができるらしい」
「ふぅん……」
精霊と共存するこの世界において、昔から『ギフト』を持って生まれてくる子供は、少なくない。
しかし……特別な力を持つ者は、例外なく排斥されると、師匠は言った。
魔術師と同じように、と付け加えて。
「……お前のオヤジさんは、瞳を隠してるだろ? そして誰にも言うなと言ってなかったか?」
「う、うん……魔法の眼鏡でいつも隠してるけど……」
「ならばその話はしない方がいい。しなくてもいい事も、この世にはあるんだよ」
「えっ?」
「魔法に関してもそうだ。興味を持つのはいいが、露骨なのは止めた方がいい。友好的な魔術師なんか、そうそういないんだぞ」
俺は少女に警告するつもりでそう言った。
しかし少女は笑いながら、俺の肩をぽんぽんと叩く。
「あたしけっこう、人を見る目はある方なの」
「は? なんだそりゃ……」
「アンタは……いい人だと思ってるんだけど?」
「悪人かもしれないぞ?」
「それはないわね。わざわざあたしを助けてくれたし、魔術師にしては腰が低くて押しに弱そうだもん」
「……ほっといてくれ」
少し抑えながらも、おかしそうにけらけら笑う少女を見て、俺はなんとなく、ミルフィを思い出す。
見た目はともかく、この少女とミルフィは、仕草がことごとく似ている。
人なつっこい性格も、クセも、髪の色も似ている。
この少女を見ると、ここ1年でやっと忘れかけていた気持ちが、鎌首をもたげて蠢くのを感じる。
それは辛くて……悲しい事だった。
「なんか、お父ちゃんに似てるかも?」
「……よしてくれ、俺はそんな歳じゃない」
「あ、そういう意味じゃなくて。人への接し方とか、雰囲気とかね」
「そりゃ、よっぽどいい男なんだな」
「顔はお父ちゃんのが100倍いいけどね」
「あ、っそ……」
「お父ちゃん、あの街の冒険ギルドのギルド長なの。今は別件で、海底神殿とかいうのを探しに行ってるんだけど……難航してるみたい」
「メシェの伝承のアレか? アレは伝承だけで存在はしないというのが通説だと聞いたが」
「それが、なんか有力な情報が見つかったとかで、スチームシティのバックアップで色々……って、これ以上はギルドの機密になっちゃうから、内緒」
「そこまで話したら内緒もないだろ……まぁ、誰かに言うつもりなんかないけど」
「そうね、アンタならきっとそうしてくれると信じてるわ」
「信じられても困るが」
「いいえ、きっと大丈夫。いい人だもん、アンタ」
「そりゃ結構な評価を頂きまして」
「話とか面白いのも似てるし、先生とかまとめ役に向いてると思うわよ?」
「止めてくれ、俺はめんどくさい事は基本的に嫌いなんだよ……」
だから……心を許してしまったのかもしれない。
そしてこの油断がなければ……ここまで奴らに接近される事はなかった。
*
それは、先頭のスカウトの悲鳴から始まった。
「え、な、なに!?」
通路に配置されていた、有翼の悪魔像が突然動きだし、先頭の集団を襲撃したのだ。
それも、かなりの数の……。
俺は状況を飲み込めず立ちつくす少女を、とっさに引き寄せ庇う。
その少女の頭があった空間を、飛来した石像の爪が薙いだ。同時に少女の髪が数本宙を舞う。
「な、なにあれ!?」
「ガーゴイルだ。普段は石像と同じなんだが、侵入者が現れるとああして襲ってくる……。あの姿になるまで、魔力すら感じないやっかいなヤツだ」
「な、なにのんびり解説してるのよっ、というか、どさくさに紛れてどこ触ってるのっ!?」
「この際気にするな……。というか、まずいな、パーティが完全に混乱してやがる」
「だからのんびりなにを言ってるのよ、仕事しなさいよ、仕事っ!!」
「……ったく、仕事じゃしょうがない」
「え……っ?」
俺は少女を抱えたまま、やれやれと頭を掻いた。
「いいか、ガーゴイルは魔術師によりマナを吹き込まれ生み出された魔法生物だ。ただの魔物と違い疲労がなく、マナが尽きるまで永遠に動く事ができる。それがどういう事か分かるか」
「そんなのわかんないわよ!」
「つまり、ただの魔物よりタフで危険。おまけに空まで飛ぶ……。ただの傭兵にゃ、荷が重すぎるって事だ」
俺は小さく息を吐く。
そして……久しぶりに体内のマナを大きく練り直していく。
「え、ええ……、な、なにこの光……?」
そんな俺に抱きかかえられたまま、少女が驚き、目を大きく見開いた。
「さすが『妖精眼』の娘だな。練り直した高密度のものとはいえ、マナが見えるのか」
「ま、まな……って……?」
「マナというモノは、この世界の全てのモノに存在する生命の根元だ。それは生物にも、石にも、水にも、空間にも、魔物にすら存在する……」
話ながら練り直したマナが、ゆっくり形を変えていく。
俺の意思により、全ての敵を穿つために。
「な、なに、これ……。なにが起きてるの……?」
「いいか、よく見ておけ。これが魔法だ。お前が見たがっていた魔法の力だ。そして……天空に住まいし、大魔導師クロウフォードが唯一無二の弟子、ウィル・フロイハイムの真なる力だ」
幾十もの雷の閃光が、まるで意思を持った竜のように俺のまわりで渦巻き、解き放たれるのを待ち望むかのように、咆哮を上げる。
その雷がやがてプラズマを生み、わき上がる静電気がちりちりと頬を撫で、髪が逆立ち、揺らす。
「幾万の雷朋よ、古き盟約に基づき、集い、弾けよ!! プラズマストライク!!」
呪文と共に放たれた、人の頭よりも大きな、集約されたプラズマが、1つも外れることなく、ガーゴイルの固い外殻を打ち砕き、元の石像に変えていく。
文字通り一瞬で、十数体のガーゴイルは動かなくなった。
「ふぅ……」
パーティ以外に動くものがないことを確認した俺は、呼吸を整えてから、抱きかかえていた少女をそっと下ろす。
「大丈夫か?」
「……………………」
目の前で起こった出来事が信じられないのか、少女はただ呆然と、砕かれた石像と、呻く仲間と、俺の顔を交互に見ていた。
「被害がでかすぎるな、一度出直した方がいい。ガーゴイルは倒したが、この先同様の罠がないとは言い切れんしな」
「……………………」
俺は癒しの雫の呪文で怪我人の処置を行いながら、ただじっと座り込む少女を見た。
少女も俺を見た。
そして……俺は後悔した。
やはり、同行すべきではなかったと。
この少女がどうなろうとも、助けなければよかったと。
少女はただじっと、俺を見ていた。
ただじっと……。
なにか恐ろしいモノを見るように……。あからさまに怯えた表情を浮かべて……。
*
結局、パーティの被害が大きすぎるのと、トラップの凶悪さに恐れをなした者が現れたために、遺跡の探索はうち切られる事になった。
俺は出発前よりも疎遠感のあるパーティからかなり離れた場所で、次の街まで行く準備を進めていた。
怪我人は出たが、死者がいなかったのが幸いと言うべきか。
魔術師がさげすまされたり怖がられるのはいつもの事だ……。だから特に、気にするような事ではない。
ただ少し……悪い夢を見ただけだ。
明日になればきっと忘れられる……。その程度の出来事なんだ……。
そう心の中で繰り返し、荷物を担ぎ立ち上がる。
「あ、あの……」
街を背に、立ち去ろうとした俺に、ひどく小さな声がかけられた。
俺は振り向きもせずに、なぜか止まった足に、この場から立ち去るように強く命じた。
「ちょっと待って、お願い、お願いよ……」
そんな俺をもう一度、声の主が引き留める。
それだけでなぜか、足が完全に止まる。
「……俺の仕事は終わったはずだ」
「で、でも、報酬もまだ……」
「仕事は失敗だろ。報酬は受け取れんさ」
「でも、でも……」
少女が困ったように口ごもる。立ちつくす俺に近づき、マントの端を掴もうとして……躊躇した。
「あ……」
そんな自分が信じられないのか、少女がじっと、自分の手を見る。
「……怖いなら無理するな」
「でも……」
「恐怖を感じる事は悪い事じゃない。恐怖心がなければ、人間は今よりもっと前に滅んでいる。探求心と恐怖心が存在しているからこそ……人は人たりえるんだよ」
「………………」
「いいか、魔法は人を癒す事もできるし、助ける事ができる。しかし……見たとおり、簡単に壊す事ができるんだよ。物も……人もな」
俺の言葉に、びくりと肩をふるわせる少女。
怖いながらも俺に声をかけるためにやってきたその勇気に、少しだけ癒され、俺は荷物を掴んだ。
「じゃあな、あとは任せる。それと、あまり派手な事は慎むようにな。お前のオヤジさんに、心配かけさせるなよ」
「…………まって……」
「……なんだ?」
少女が恐る恐る、マントの端を掴む。
思ったよりも強く、マントが握られるのが分かった。
「無理はするなって言ってるだろ……?」
「だって……」
「見た目はただの人間でも、魔導師の力は剣や弓なんかと比べものにならない。そんな力を持つ者を恐れない人間なんか、いないんだよ」
「ちがう、ちがうの……」
「いや、違わない。だがそれもまた……人間だから感じる感情だよ」
俺はできる限り優しく、諭すように言う。
しかし少女は頑なに頭を横に振り、震える声で、こう言った。
「怖いと思った。ホントに……怖いと思った……。魔法が……それを平然と使うアンタも……。戦いも、全部怖いって……」
「そうだな、怖い……。俺だって怖いんだよ。この力がいつか、誰かを滅ぼす事になるかもしれない……。闇に堕ちたたくさんの魔術師のようにな」
「………………」
「でも……力は正しく向ける事で、より多くの人を救う事ができる。俺が過去誓ったように、誰かを守るために……魔法を使う事だってできる」
「あたしだって……助けられた……」
「偶然な。無視する事だってできた。ガーゴイルのことだってそうだ。結果的に死人は出なかったが、俺には怪我人を出さずに済ます力があった。でも、できなかった」
「それは、アンタのせいじゃない……」
「俺のせいなんだよ。それが力を持つ者の進むべき道。俺は……まだまだ未熟なんだと思い知ったよ」
「違う、絶対に違うよ、そんなの……」
「……達者でな。あまり他人に心を許すな。長生きしたいなら、特にな……」
「まってよぉ!?」
少女が叫び、マントを掴む手が放れる。
そして少女はその場に崩れ落ちて、大粒の涙を流した。
「ごめんなさい、ごめんなさい……。ありがとうって言いたかったのに、言えなかった……。言わなくちゃいけないのに、言えなかった……」
「気にするなと何度も言ってるだろ」
俺は振り返り、ボロボロと涙を流す少女に声をかける。
「あたしのお父ちゃん、いつも言ってた……。人は自分と違う力を持つ人を恐れ、排斥しようとするって……。あたし、よく分かってなかった……。お父ちゃんの言ってる事も、なんでだろうって考えてた……。でも、今分かった……お父ちゃんの言ってた意味も、お父ちゃんがどんな気持ちでいたのかも……」
ボロボロ涙を流しながらしゃくり上げる少女の頭を、俺はぽんぽんと撫でてやる。
昔、同じように泣く ミルフィにやっていたように。
「お前は……優しいな。俺の妹に……そっくりだ」
「いもうと、さん……?」
「ああ。髪の色も、仕草も……泣き虫な所もそっくりだ」
「あ、あたしは泣き虫じゃ……無いと思ってた、けど……そうなのかな……そうかも……」
少女がゆっくり、自分に言い聞かせるように言う。
「……その気持ち、大事にしておけ。その気持ちを持つ者は、この世界に必要だ」
「うん……ありがとう……」
少し泣きやんだ女の子が、それでもすすり泣きながら上目遣いで俺を見て言う。
「ねぇ……ウチのギルドに来る気、ない……? アンタならきっと、お父ちゃんも喜ぶし、あたしも……」
「すまんが、それはできない」
「えっ……」
「俺はまだ修行中だし、行きたい場所もたくさんある。今足を止める事はできないさ」
「あ…………な、なんだ、そういう事か、あたしてっきり……」
「これでもまだ、見習いだからな。それに……」
「それに……?」
「……アンタの優しさは、俺には眩しすぎる」
「な、なにそれ……」
「居心地がよすぎるんだよ。それでは俺が修行に出た意味がなくなっちまう」
「意味……?」
「俺は俺にけじめを付けるために旅に出た。俺の中に生まれた疑問と欲望をコントロールするために旅に出た。だから……」
「だから……?」
「優しさに、俺はたぶん溺れちまう。それだけはできないし……したくない」
「そ、う……か……ぁ……」
少女の顔が落胆に変わる。しかしそれはすぐに眩しすぎる笑顔になった。
「残念っ。有望なギルド員をみすみす逃しちゃったかっ」
「なんだそりゃ……」
「結構、勇気を振り絞ったんだけどなぁ~……」
「あん? 聞こえなかったが……」
「なっ、なんでもありませーんっ」
少女が立ち上がり、やたら短いスカートについたほこりを払う。
「ねぇ、ウィル?」
「なんだ?」
「いつか、いつかね…………この街に戻って来る事もあるわよね……?」
「どうだろうな、約束はできないが」
「ダメ……?」
「……そうだな。お前がもっと女らしくなって、立派にギルドを運営してるという噂を聞いたら……」
「聞いたら……?」
「顔ぐらい、出してやってもいいか」
俺は少し恥ずかしくなり、視線を外して背を向けた。
「ホント!? 絶対、ぜーったい、約束よ! あたし、もっともっと女の子らしくなる! ギルドだって今よりもっと大きくしてみせる! だから絶対、あたしに会いに来て!」
「気が向いたら、な」
俺は軽く手を振り、背中を向けた。
背後から聞こえる少女の声に励まされるように。
一度も振り向かずに。
ただ……少女がユシィと呼ばれていたことを……ふと思い出した。